
🔥夏バテ予防は「火を消す」より「火を守る」
夏真っ盛り、喉越しの良いそうめんやキンキンに冷えたビール、甘いアイスクリームが美味しい!冷たいものが手放せない!という方も多いのではないでしょうか。
でも実は、“冷やすこと”でのは癒しは一時的なもので、それだけでなく夏バテを招く原因になる場合があるのです。
☀️夏は「消化力」が落ちる季節
アーユルヴェーダでは、夏は特に消化力が低下しやすい時期と考えます。
消化力が落ちるということは食べたものがうまく消化されないということ。
消化されないものは未消化となり体に栄養が吸収されないだけでなく、体内に毒素として蓄積され体の不調を招く原因となるのです。
夏バテしないように栄養のあるものを食べなきゃ!と頑張って食べた後、胃もたれや怠さ、疲労を感じたことがある方は、こういったことが原因かもしれません。
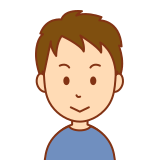
ちょっと夏バテ気味かなぁ。夏バテには鰻!辛いもの!お肉!スタミナたっぷりつけなきゃ!!
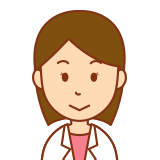
消化に重いものばかりね!食欲が低下しているのにそんなものを無理に食べたら消化力がさらに低下してしまうわ。まずは消化力を整えることを考えて。
❄️冷たいものが火を消してしまう
ただでさえ消化力が落ちているときに、冷たい飲み物や食べ物をたくさん摂ってしまうと…
まるで、小さくなった火に氷水をかけるようなもの。
(アーユルヴェーダではお腹の中に火の神様がいて、食べたものを燃やしてくれると考えます。)
一時的にスッキリしたように感じても、体の内側ではアグニがしゅん…と弱まり、
- 食べたものがうまく消化できない
- 栄養が吸収されない
- 未消化物(アーマ)が体に蓄積される
といったことが起こりさまざまな不調の原因につながってしまいます。
実際に、食欲がない、だるい、元気が出ない…そんな「夏バテ症状」は、“消化がうまく働かず、体に未消化物(毒素)が溜まっているサイン”なのかもしれません。
冷たいものだけでなく、消化に負担のかかるものを控え、まずは自分の消化力を労る選択が重要です。
☕大切な火を守る薬「スパイス」を日常に
夏バテ予防におすすめなのがスパイス。
スパイスには冷性・温性があるので、スパイスならなんでもいいわけではなく熱を冷ましながら消化力をサポートしてくれるものが理想的。
(冷性といっても身体を冷やすのではなく冷ます作用のため、冷えが気になる方もご安心を。)
つまりピッタ(火)を刺激しすぎないスパイスやハーブを選ぶことがポイントです。
冷房の心地よさの裏側で実は冷えている体、芯を温め余分な熱を放出してくれるので
飲んだあとはシャッキリ、内側から元気が湧いてくるような感覚になるはずです。
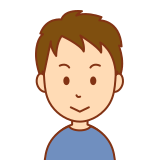
スパイス料理なんて僕には無理だよ。
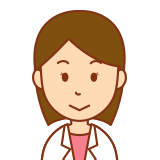
スパイスを使ったマサラチャイならお料理が苦手でも簡単に作れるわ
🍵夏のスパイスチャイ簡単レシピ(1人分)
材料
- 水 :100ml
- ミルク:100ml
- 茶葉:大さじ1程度
- スパイス(できればホール):(コリアンダー 、カルダモン 、フェンネル 、クローヴ)
- 生姜薄切り :2枚程度
- ハーブ:ローズペタル 、リコリス粉
- お好みで甘味(きび糖など)
作り方
1.スパイスを砕き、かるく炒る。
2.1に水とスパイスと生姜を加え火にかける
3.香りが立ち水が茶褐色になるまで煮出し茶葉、甘味を加える
4.ミルク、ローズペタル、リコリス粉を加える
5.ふつふつと煮込み噴きこぼれる手前で火から離すを3〜5回繰り返す
6.お好みで甘味を加えたあと、茶漉しでこしながらカップへ注ぐ
→高い位置から注ぎ空気を含ませるとより美味しく感じるかも♡
※豆乳は製品によっては煮立たせると分離するものがございます。
スパイスやハーブは全て揃わなくて◎
ミルクと水の割合はお好みで調整してください。(ミルクを減らした方がより消化に軽いです。)
生蜂蜜は加熱NGのため勧められません
🌿まとめ:「夏は冷やす」ではなく「火を守る」
- 消化できない=食べたものをエネルギーに変換できない
- 冷やしすぎると、アグニが弱り、体も心もどんより重たくなる
- 火を守れば、自然と巡りがよくなり、元気が湧いてくる
「スパイスチャイを味わう」ことは、“お腹の中の火の神様”に感謝を捧げる、やさしいセルフケアのひとつかもしれません。
また、夏の不調は秋にはさらに身体を枯渇させ不調を招きます。
軽視せずに根本を整えるケアを行ってくださいね。
どうぞ、この夏は“火を守る”選択を。
ご自分や大切な人へ丁寧にチャイを淹れる時間を楽しんでみてくださいね。
きっと心も豊に整っていくことを感じるでしょう。
最後までお読みいただきありがとうございます。
本日もどうぞ、ご自愛くださいね。


コメント